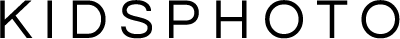東京の秋葉原駅や御茶ノ水駅から、徒歩5分の場所に位置する江戸の守り神、神田明神。
正式名称は神田神社になります。
「勝負運が上がる!」と過去には多くの武将から信仰を集めましたが、最近ではアニメの聖地としても有名です。
KOBO
今回はそんな神田明神の「歴史」と「見どころ」について紹介したいと思います。
目次
神田明神の歴史

1303年:平将門が相殿神とされる。
1616年:現在の地に遷座
1782年:権現造の社殿が造営
1872年:社号が「神田神社」に変わる
1874年:平将門が祭神から外され、少彦名命が勧請される
1923年:関東大震災により社殿が焼失
1984年:平将門が祭神として復帰
2019年:「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」に認定
神田明神は730年に現在の東京都千代田区大手町にあたる、武蔵国豊島郡芝崎村で創建されました。
出雲系の氏族である真神田臣(まかんだおみ)が、大黒様こと大己貴命(おおなむちのみこと)を祀ったことが始まりです。
1303年になると平将門の乱で命を張って、民衆を守った平将門を相殿神として祀ることにしました。
平将門神は数々の武将から信仰を集め、特に徳川家康が戦勝の祈祷をしたところ、9月15日の神田祭の日に天下統一を果たしたのは有名な話です。
それ以来、神田祭は徳川家によって縁起の良い祭礼として、絶やすことなく執り行うよう特別扱いされました。
江戸の総鎮守

江戸時代の神田明神は江戸の総鎮守として信仰を集めます。
そのため何度か場所を移し1616年に現在の場所へ遷座しました。
神社が国家の管理下に入る明治時代、1872年には神田明神から正式名称を神田神社に改めます。
また、この時に江戸城を皇居に定めた、明治天皇が神田明神に参拝するようになります。
この時に「主君にそむく臣下・逆臣である平将門が祀られているのは、いかがなものか?」といった意見が出てきます。
そのため1874年に平将門が祭神から外されます。
代わりに少彦名命(すくなびこなのかみ)の分霊を大洗磯前神社(おおあらいいそさきじんじゃ)から向えることになります。
社殿焼失を乗り越えて
1923年には関東大震災で、1782年に建てられた権現造の社殿が焼失します…
鉄筋コンクリートの強固な社殿として、再建されたのは1934年のこと。
1984年になると嘆願により、平将門が祭神として復帰します。
平将門神はもともと市民の間でも人気が高く、祭神として復帰を願う人が数多くいました。
KOBO
特に1976年に放送された平将門を主人公とする、NHK大河ドラマ「風と雲と虹と」が祭神復帰への大きな後押しとなったようです。
アニメの舞台にも!?
2010年代に入ると神田明神は「ラブライブ!シリーズ」「シュタインズ・ゲート」など、アニメ作品の舞台にもなります。
秋葉原に近いこともあり、聖地巡礼のために神田明神を訪れる人が数多く見られるようになりました。
2019年に「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」に認定されたように、現代の神田明神はアニメの聖地として代表的な存在となりました。
神田明神のご利益

・国土経営
・夫婦和合
・健康祈願
・商売繁盛
・除災厄除
・縁結び
・勝運
神田明神では「大己貴命・少彦名命・平将門」これらの神様が祀られています。
大己貴命は別名・大黒様。国土開発や医療、縁結びの神様として知られています。
少彦名命は別名・恵比寿様の名で知られています。
商売繁盛や開運招福の神として有名です。
そして、平将門は除災厄除や勝運の神様。
過去には多くの武将から信仰を集めていました。
KOBO
特に徳川家康が戦勝の祈祷をし、その後天下統一を果たしてからは「平将門神に祈願すると勝負に勝つ」と言われるようになりました。
神田明神の見どころ
神田明神には沢山の見どころがあります。
ここでは、それらをピックアップして紹介したいと思います。
隨神門

こちらは隨神門(ずいしんもん)と言い、神域に邪悪なものが入り来るのを防ぐ天皇の神をまつる門です。
・外回りには四神(朱雀・白虎・青龍・玄武)
・内側には因幡の白兎(いはんのしろうさぎ)
このように神田明神の隨神門には、大黒様の神話をモチーフにした彫刻が飾られています。
外側正面には豊磐間戸神(とよいわまとのかみ)と櫛磐間戸命神(くしいわまとのかみ)の隨神像があります。
この像は安土桃山時代から江戸時代に活躍した、加藤清正公お手植えの樹齢500年の楠で作られたものです。
KOBO
実はこの像は、パナソニックの創業者の松下幸之助氏により奉納されたものです。
銭形平次の碑
時代劇でおなじみの銭形平次の碑(いしぶみ)です。
銭形平次は近年では、テレビの時代劇のイメージが強いと思います。
しかし、原作は銭形平次捕物控(ぜにがたへいじとりものひかえ)といった野村胡堂(のむらこどう)氏による小説です。
銭形平次は御用聞き(ごようきき)という、今でいう警察の非公認の協力者のような役割で、卓越した推理力で鮮やかに事件を解決します。
その銭形平次が住んでいた家が小説では「神田明神の下」という設定なのです。
こちらの碑は日本作家クラブが発起人となり建てたものです。
角田竹冷の句碑
こちらは角田竹冷(つのだちくれい)の俳句が書かれた石碑です。
「白うをや はばかりながら 江戸の水」
「白魚もとれる神田川の水は、恐れおおくも、その昔将軍さまのお茶の水にも召されたという江戸一番の名水である」という意味です。
角田竹冷は明治期の俳人として有名な、あの正岡子規と競い合っていたことで有名です。
角田竹冷は今の弁護士にあたる代言士として働きながら、俳人として活動をしていました。
後に旧神田区の初代区会議長や衆議院議員を務め、政治家としても活動しました。
獅子山

江戸時代中期に活躍した名工・油売藤兵衛が、生涯でわずか3つしか造らなかったものの中の1つが、この獅子山です。
獅子は「生まれたばかりの子を深い谷に落とし、這い上がってきた生命力の高い子供のみを育てる」といった言い伝えを造形化したものです。
上にいる二頭の親獅子は古い時代のものですが、下の子獅子は新しい時代のものです。
関東大震災により、子獅子だけが紛失してしまったようです。
子獅子は平成元年1989年に天皇即位を記念して再建されたようです。
えびす様尊像

こちらは神田明神で祀られている、恵比寿様こと少彦名命の尊像です。
恵比寿様と言えば「福耳で鯛を抱えた恰幅の良いお爺さん」といったイメージが一般的だと思います。
ただ「えびす」と呼ばれる神様は実は複数あり、色々な神様を恵比寿様と呼んでいたりするのです。
神田明神のえびす様こと少彦名命は、一寸法師のルーツになったと言われています。
「海のかなたから、小さな木の実の殻の舟に乗って来臨され、小さいお姿ながら大黒様と力を合わせ、この日本という国をお作りになった」
このような話があります。
「大きな体の恰幅の良いお爺さん」ではなく「小さいお姿」なのです。
少彦名命は海の神であり、医薬や酒造りの技術を広めたと言われています。
恵比寿様を少彦名命とするのは少数なので、神田明神のえびす像は全国的にも珍しい像なのです。
まとめ

KOBO
以上、神田明神の「歴史」と「見どころ」について紹介しました。
江戸の総鎮守として、古くから信仰を集めた神田明神ですが、現代ではアニメとのコラボグッズを販売したりイベントなども開催しています。
現代の新しい文化も上手く取り入れていて、1度行けば決して忘れないようなインパクトのある神社です。
是非、神田明神に足を運んでみてください。